肉体派ニュー・ウェイヴ・バンド
DCブランドの洒落たスーツに身を包み、カフェ・バーが続々誕生していた夜の町に繰り出すことが都会的とされていた、そんな80年代のバブリーで華やかな東京。YMOらの活躍によって音楽が新しい時代のポップ・カルチャーを伝える一方、東京ロッカーズ以降インディー・シーンはより混沌とした面白さを伝えるようになっていた。PINKはそうした刺激的な東京の中にあって、どのようなポジションで活動している実感があったのだろうか。
「例えば、僕らは(町田)町蔵や(遠藤)ミチロウさんとも仲が良かったけど、YMO周辺とかプラスチックスとかともつながっていた」(ホッピー)
「あの頃って ”ツバキハウス” ”ピテカントロプス” ”インクスティック” なんてクラブがあったわけだけど、僕らは”ツバキハウス”がメインとはいえ、なんだかんだでどこでも出入りしてた。つまりそういうことだったんだよ。でも、デビューする頃になると、自然と色々見えていくようになったのね。例えば、俺らもファンクばっかりやってるのが飽きちゃって(笑)、ポリスもカッコいいしロキシー・ミュージックもいいなって感じで色々やりたくなってきて、ファンクにこだわらなくなってきたんだけど、それによって、メンバー個人個人の力量で勝負するっていうか、演奏力で聴かせることができるバンドになっていった。みんな巧かったからね。スタンリー・クラークとかジョン・マクラフリンとかコピーしてたんだよ(笑)」(福岡)
「確かに僕もパンクの洗礼受けてベースなんて一切触らなかった時代もあったのね。でも、PINKを始めてやっぱスラップ・ベース解禁だな!ってなった(笑)。で、気がついたら残ったメンバーはエキスパートばかりになって・・・それがそのままデビュー以降のPINKのオリジナリティになったんじゃないかな。当時、ユニークでクールなバンドは確かにいたけど、大抵ヘナチョコだった(笑)。俺ら力量肉食系軍団だったから楽勝だって思ってたの(笑)。スキル、経験値、パワー、すべてにおいて、ヘタウマがイイっていう当時の価値観を超えようとしていたところは今思えばあったかもしれないね」(岡野)
吉田美奈子や布袋寅泰らも参加した85年のファースト・アルバム『PINK』は、自他共に認める逞しさ溢れる肉体派ニュー・ウェイヴ・バンドとしての本領がいきなり発揮された力作だ。基本的に、殆どの楽曲を書いているのは福岡。歌詞は吉田美奈子や宇辺セージ(UWE SAGE)が担当することが多かったが、多くの場合、メロディに強いこだわりを見せる福岡が全体像を伝えて書いてもらったという。が、”チャラいイメージ”で名付けたというPINKというバンド名の由来とは裏腹に、歌詞世界は翳りのあるロマンティシズムを色濃く落としたシュールなトーンで統一されている。
「僕はどちらかというとイギリスの音楽が好きで、雰囲気もああいうちょっとダークなものが好きだったから、メロディのイメージに合った歌詞を求めていたんだけど、美奈子さんは音のイメージをすぐ理解してくれました。とはいえ、曲を作る時はほとんど感覚というか即興でパッと思い浮かんだものを作り上げていく感じでほとんど意識的ではなかった。メロディは自分の頭の中に入っているから、コード進行だけメンバーに渡して演奏してもらう。そこから先は丸投げだったからメンバーは大変だったんじゃないかな」(福岡)
「確かに先に岡野くんがギターとベースを両方兼ねたような音を入れちゃうから、まずそこギターが要らなくなる(笑)。キーボードはまだ音色が違うから余地があるけど、それでもドラムとベースを録音してる時に一緒に入れないとチャンネルが限られてるから入れる場所がなくなっちゃう(笑)。てな感じで、毎度強いもの勝ちって感じのレコーディングだったね(笑)」(ホッピー)
「でも、決してエゴのぶつかり合いじゃなかった。みんなちゃんと人の音を聴ける。じゃなかったら、今聴いてもこんなにバランスのとれたアンサンブルにはなってないと思うよ」(福岡)
「ただ、今思うとビックリするくらい制作費はつぎこんでいた。そういう時代だったんだよね。でも、だからって売れないといけないとかヒットを出せというようなプレッシャーを受けたこともなかったんだ。そういう意味ではすごく恵まれた環境にいたんだと思う。間に入ってアドバイスしてくれたプロデューサーの佐々(馨)さんの力も大きかったね」(岡野)
解散の理由を改めて問うと、全員笑いながら「売れなかったからじゃない?」と苦笑する彼ら。実際はどうであれ、結局、バンド自体は89年に凍結という形で幕を下ろすこととなった。オリジナル・アルバムは『PINK』(85年)、『光の子』(86年)、『PSYCHO-DELICIOUS』(87年)、『CYBER』(87年)、『RED&BLUE』(89年)の5枚。だが、『CYBER』以降は渋谷やスティーヴが脱退して結束が崩れた上、次第に個別の作品をまとめるような状態となっていった。発売されたばかりの『ULTIMATE~ゴールデン・ベスト』にも最後の2作品からは収録されておらず、実質最初の3枚がPINKと呼ぶにふさわしいということなのだろう。その後、プロデューサーとしてひっぱりだこの岡野、神楽とコラボレートするなど自在な活動が印象的な福岡、自分でレーベル運営しながらプロデュースやソロ活動など広く視野に入れて動いているホッピー・・・と、今なおそれぞれに活躍の場は多いが、結成30年が見えてきた今、再び手を組む可能性はあり得るのだろうか。
「カッコ悪いよ~(笑)。もっと新しいことやっていたいじゃない?やるなら全然違う名前でやりたいな」(福岡)
「うん、今ならもっと全然違うことができると思うしね」(ホッピー)
「今、PINK再結成なんてお笑いだよね。あ、でも、1億円貰えるなら何だってやりますよ(笑)」(岡野)
[9月21日 青山・ワーナーで]
取材・文=岡村詩野

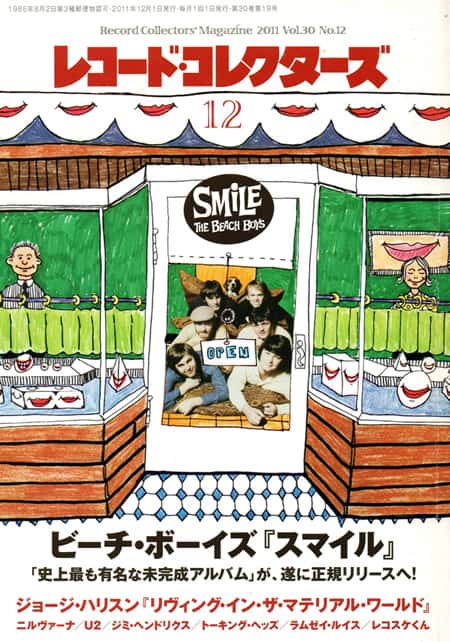 「レコード・コレクターズ」2011年12月号掲載
「レコード・コレクターズ」2011年12月号掲載



