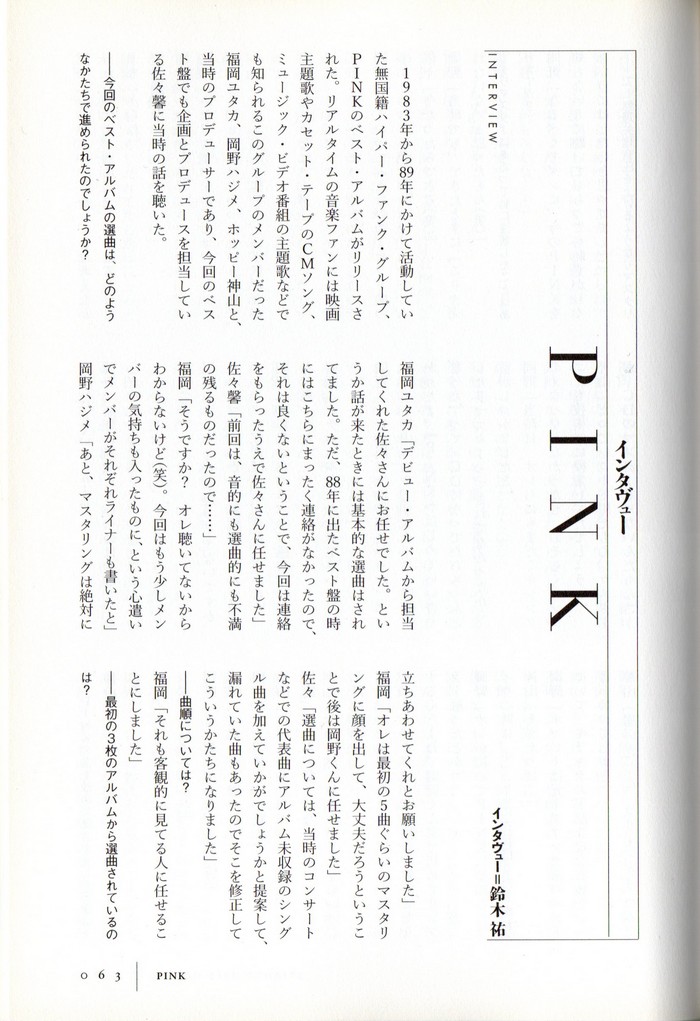1983年から89年にかけて活動していた無国籍ハイパー・ファンク・グループ、PINKのベストアルバムがリリースされた。リアルタイムの音楽ファンには映画主題歌やカセット・テープのCMソング、ミュージック・ビデオ番組の主題歌などでも知られるこのグループのメンバーだった福岡ユタカ、岡野ハジメ、ホッピー神山と、当時のプロデューサーであり、今回のベスト盤でも企画とプロデュースを担当している佐々馨に当時の話を聴いた。
―――今回のベスト・アルバムの選曲は、どのようなかたちで進められたのでしょうか?
福岡ユタカ「デビュー・アルバムから担当してくれた佐々さんにお任せでした。というか話が来たときには基本的な選曲はされてました。ただ、88年に出たベスト盤(注:「FINAL MIX」)の時にはこちらにまったく連絡がなかったので、それは良くないということで、今回は連絡をもらったうえで佐々さんに任せました。
佐々馨「前回は、音的にも選曲的にも不満の残るものだったので・・・・・」
福岡「そうですか? オレ聴いてないからわからないけど(笑)。今回はもう少しメンバーの気持ちも入ったものに、という心遣いでメンバーがそれぞれライナーも書いたと」
岡野ハジメ「あと、マスタリングは絶対に立ちあわせてくれとお願いしました」
福岡「オレは最初の5曲ぐらいのマスタリングに顔を出して、大丈夫だろうということで後は岡野くんに任せました」
佐々「選曲については、当時のコンサートなどでの代表曲にアルバム未収録のシングル曲を加えていかがでしょうかと提案して、漏れていた曲もあったのでそこを修正してこういうかたちになりました」
―――曲順については?
福岡「それも客観的に見てる人に任せることにしました」
―――最初の3枚のアルバムから選曲されているのは?
佐々「全部のアルバムから、とは考えなかったんですよ。別にヒット曲があるわけじゃないからね」
(全員爆笑)
福岡「すいません(笑)」
佐々「いや、スマッシュ・ヒットはあってもベスト10ヒットはなかったという意味で。ヒット・シングルを作ろうという気はなかったし」
岡野「なかったね」
福岡「でも、クリスマス・シングルを作ろうということになって・・・・・」
岡野「そういってみたものの、ヒット曲の作り方がわからず(笑)」
佐々「今だったらできる(笑)」
岡野「当時でも、できたときに『こりゃ売れないな』と思ったもん(笑)」
―――リマスターにあたって特に注意したことはありますか?
岡野「なるべくモダンに、今のPINKを知らない人に聴いてもらっても恥ずかしくない音にはしたいと思ってました」
―――でも無理矢理音圧を上げるようなリマスタリングにはしていませんよね。
岡野「無理に過激にというのはやめて、なるだけ元の音をブラッシュアップするというかたちにしました。一応そのへんはオトナに(笑)」
福岡「スネアの音が違うじゃないですか。リバーブが深いから、無理にレベルを上げるとリバーブ音ばっかりが目立つから」
岡野「80年代のあのリバーブ感は、時代だなと思ったな」
福岡「ナチュラルなリマスターでいいと思う」
岡野「オレの周りでは評判良かった」
ホッピー神山「いやリスナーにも評判良かったよ。『PINKがはじめていい音で聴けた』って。CDになってからちゃんとしたリマスターってされてなかったから、音がしっかりしたと」
岡野「当時は、オレらにもまだミキシングのノウハウがなかったし、おそらくエンジニアも技術的に模索してたでしょうし」
神山「だってレコード用だもん、マスターが。CDのマスターじゃないんだもん」
―――PINKの曲を改めて聴きかえした印象は?
神山「昔やってた曲ってだけですけどね(笑)」
福岡「ホッピーさんの思いはライナーにたっぷり書いてあるから」
岡野「よく覚えてたね、あれだけ」
福岡「スゴいなと思った」
岡野「オレ、ほとんど覚えてないよ」
神山「自分のことも?」
岡野「ほとんど覚えてない。海パンはいてスタジオ行ったこととか、どうでもいいことだけ(笑)」
福岡「オレもそうだけど、デビュー前のことのほうがインパクトが強くて覚えてたりするんだよね。岡野くん家で初めてサンプラー触ったとか」
岡野「オレが初めてPINKに参加したライブの時に、ホッピーに衣装借りたとかね」
神山「そうだっけ?」
岡野「ホッピーは元々ファンク系のバンドにいて、キラキラの下品な(笑)衣装をいっぱい持ってたから」
神山「思いだした。ラリー・グラハムだろ?って(笑)」
岡野「そのときはベース3人いたからね」
神山「全部で12~13人いて、その感じがおピンク兄弟だった」
岡野「歌詞もみんな・・・・・」
福岡「デタラメで」
―――それが82年ごろ?
福岡「83年かな」
岡野「それでメジャー・デビューは84年か」
福岡「でも、それでヒットを出してっていうイメージが湧かなかったよね」
岡野「何万枚売れたら幸せなるとかいうイメージはなかった」
福岡「金銭的なことは考えてなかったですね」
神山「PINKでは暮らせなかったからね」
岡野「バンドで食おうなんてカケラも思ってなかったから、みんなスタジオやCMの仕事を個人で受けてたからね」
福岡「でも、もし売れてたら曲はほとんどオレが書いてたから・・・・・」
岡野「もう大儲け」
福岡「そうするとほかのメンバーとは絶対不和になってたじゃん(笑)。でも、結果的には印税来なかったから」
岡野「なんで? だまされてたんじゃないの?」
佐々「オレの顔見るなよ(笑)」
岡野「でも、改めて聴くと売れるための方法を知らないからこそやってるアレンジとか曲の作り方はおもしろいね。今はもうできないね。だって、全曲フェイド・アウトだよ。今なら『テレビやラジオのこと考えてエンディングつけとけ』って絶対いうもんね(笑)。エンディングのある曲って2曲ぐらいしかなかったよ」
福岡「岡野くんとリマスタリングの時話したんだけど、PINKの曲にはカウンター・メロディが多い。今のヒット曲ってカウンター・メロディがないよねって」
神山「カウンター・メロディ入れられないよ、今の日本の曲は。パートごとに脈絡なく作られてるから、ウラを通して流れるものって入れられない。我々は一曲通して作ってたじゃん」
岡野「基本的にワン・コードっぽいよね」
福岡「モードな感じなんだよ」
神山「サビはフックみたいなもんでね」
福岡「かといって当時流行ってたフュージョンとも違ってたし」
岡野「フュージョン的なアティチュードは嫌ってたもんね」
福岡「そうはいっても、みんな多少は聴いてたんだけどね(笑)」
岡野「いや、みんな聴いててリスペクトはしてたんだけど、ポップ・フュージョンに対する嫌悪感はあった」
神山「でも、あっちはメガ・ヒットしたんだよ(笑)」
福岡「でも、オレたち5年早く生まれてたら、かなり違っただろうね」
岡野「まあ、そうだろうね」
―――PINKの<血気盛んな若者たち>というイメージからは、その一世代上のミュージシャンたちへの対抗心も感じられるんですが・・・・・。
岡野「その上の世代から見ると、オレたちはチャラかっただろうね。でも、上の世代のどうしてもぬぐいきれない真面目さに対して、笑いながら過激なことをやろうという意識はあったかも」
福岡「オレはそこまで世代的なことは考えてなかったかな。ただ、他人と違うことをやらなきゃ、というのはあったと思う。何か新しいことをやろうという意欲はスゴかったんじゃないかな、あの時代は」
岡野「仲間からの影響もデカかったしね」
福岡「極端にいうと、ヘンだったらヘンなほどいい、という空気だった(笑)。ただヘタウマ系のヘンさにはかなわないと思った」
岡野「テクニックはないけど、センスはすごくいい、という価値観においてはPINKは異常にテクニックがあったから、すごく特殊ではあったね」
福岡「それに対しては、ちょっと逆コンプレックスがあったかも(笑)」
岡野「おしゃれだけにはなりきれないミュージシャンシップがね。でも、テクニックはPINKの最大の強みだとも思ってたよ」
福岡「もちろん、それはメンバーみんなが共通していた認識だったと思うけどね」
岡野「当時、複数のグループが参加するイベントなんかに出ても、リハの時点でもうオレたちの勝ちが決まってたじゃん」
福岡「そう、結局は売れる売れないよりも、そいういう狭い世界でのアイデンティティの確立の方が大きかったんですね(笑)」
岡野「それは売れないわ(笑)。いちばん売れないパターン(笑)」
神山「ピテカンとかね(笑)」
岡野「そんなとこで勝ってどうする、って説教するだろうね。今のオレなら(笑)」
(インタビュー=鈴木 祐)

1985年発表のデビュー・アルバム『PINK』から6曲。86年発表の2作目『光の子』から5曲。87年発表の3作目『PSYCHO-DELICIOUS』から3曲。さらに、87年に発表された12インチ・シングルと、同じく87年のクリスマス・シングルのカップリング曲(映画『ハワイアン・ドリーム』主題歌)という曲で構成された16トラック収録のベスト・アルバム。
人種熱、爆風銃、東京ブラボー、ショコラータといった東京を拠点に活動していたファンク/ニューウェイヴ・バンドの若き精鋭たちによる新たなユニットのサウンドは「無国籍」と形容されたが、そこにはメンバーそれぞれの音楽体験とミュージシャンとしてのキャリアがこれでもかと濃縮され、詰め込まれていた。個々の楽曲については、メンバーも驚嘆したホッピー神山による詳細なライナー・ノーツ以上に語るべきことはないが、ほぼ四半世紀を経た現在、彼らの音楽を聴くと、<最先端>や<テクニシャン集団>といった鎧の下にあった、パンクやギター・ポップと通底する「がむしゃらな青春の音楽」としての爽快感が漂うことに、改めてきづかされるはず。
(鈴木 祐)
 「ストレンジ・デイズ」2011年12月号掲載
「ストレンジ・デイズ」2011年12月号掲載

ワーナーミュージックジャパンのアルバム紹介ページ(外部リンク)>>