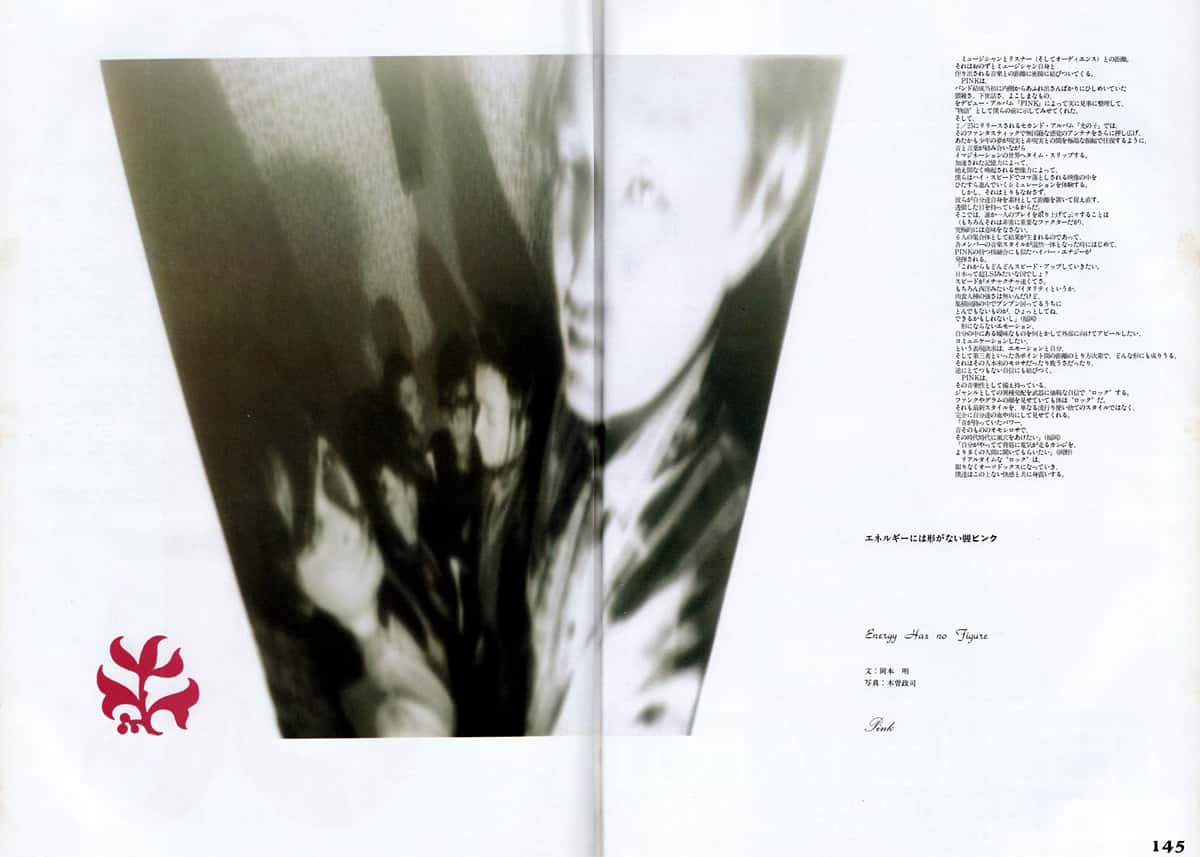
ミュージシャンとリスナー(そしてオーディエンス)との距離。
それはおのずとミュージシャン自身と
作り出される音楽との距離に密接に結びついてくる。
PINKは、
バンド結成当初に内側からあふれ出さんばかりにひしめいていた
猥雑さ、下世話さ、よこしまなもの、
をデビュー・アルバム『PINK』によって実に見事に整理して、
”物語”として僕らの前に示してみせてくれた。
そして、
2/25にリリースされるセカンド・アルバム『光の子』では、
そのファンタスティックで無国籍な感覚のアンテナをさらに押し広げ、
あたかも少年の夢が現実と非現実との間を極端な振幅で往復するように、
音と言葉が絡み合いながら
イマジネーションの世界へタイム・スリップする。
加速された記憶力によって、
絶え間なく喚起される想像力によって、
僕らはハイ・スピードでコマ落としされる映像の中を
ひたすら進んでいくシミュレーションを体験する。
しかし、それはとりもなおさず
彼らが自分達自身を素材として距離を置いて捉え直す、
透徹した目を持っているからだ。
そこでは、誰か一人のプレイを取り上げて云々することは
(もちろんそれは非常に重要なファクターだが)、
究極的には意味をなさない。
6人の集合体として結果が生まれるのであって、
各メンバーの音楽スタイルが混然一体となった時にはじめて、
PINKの持つ核融合にも似たハイパー・エナジーが
発揮される。
「これからもどんどんスピード・アップしていきたい。
日本って超LSIみたいな国でしょ?
スピードがメチャクチャ速くてさ。
もちろん西洋みたいなバイタリティというか、
肉食人種の強さは無いんだけど、
集積回路の中でブンブン回ってるうちに
とんでもないものが、ひょっとしてね、
できるかもしれないし」(福岡)
形にならないエモーション、
自分の中にある曖昧なものを何とかして外部に向けてアピールしたい、
コミュニケーションしたい、
という表現欲求は、エモーションと自分、
そして第三者といった各ポイント間の距離の取り方次第で、
どんな形にも成りうる。
それはその人本来のモロサだったり危うさだったり、
逆にとてつもない自信にも結びつく。
PINKは、
その音楽として備え持っている、
ジャンルとしての異種交配を武器に強靭な自信で”ロック”する。
ファンクやグラムの顔を見せていても体は”ロック”だ。
それも最新スタイルを、単なる流行り使い捨てのスタイルではなく、
完全に自分達の血や肉にして見せてくれる。
「音が持っていたパワー、
音そのもののオモシロサで、
その時代時代に風穴をあけたい」(福岡)
「自分がやってて背筋に電気が走るカンジを、
より多くの人間に聞いてもらいたい」(岡野)
リアルタイムな”ロック”は、
限りなくオーソドックスになっていき、
僕達はこの上ない快感と共に身震いする。
文:岡本 明
写真:木曽政司
 「Player」1986年3月号掲載
「Player」1986年3月号掲載


