僕達の住んでいる東京をテーマに、CDの収録時間をフルに使った作品を作ろう―これがピンクの新作のコンセプトである。タイトルは『サイバー』。彼らの音楽性を考えた場合、あまりに出来すぎたタイトルではある。しかし、メンバーの曲を作曲者自らがリーダー・シップを発揮していく「作家主義」的手法を取る事によって、余りにバラエティーに富んでしまった楽曲群を一つの作品に集約する為の、苦肉の策ではないだろうか。ピンクにとってターニング・ポイントになるはずの4th.アルバムの事を中心に、そのサウンド・プレゼンスの中枢である岡野ハジメ(B)とホッピー神山(Key)が、ピンクのアイデンティティーを語る。

―――今回、ピンクの曲では初めて二人がリード・ボーカルを担当していますね。
岡野ハジメ:その点は非常に楽しかった。今まで歌う事には抵抗があったんだけど。先ず、自分の声は好きじゃなかったし、声を手段にメッセージを表現する事が分からなかったんだね。その辺をクリアーした点では、僕にとって有意義な年だったと思います。
ホッピー神山:前のバンドでは歌った事あるけど、ピンクでは初めて。元々、僕はキーボード好きじゃないから・・・(笑)。キーボード以外ならギターでもボーカルでも、何でもいい。歌自体、好きだし。今までピンクでも、ライヴではコーラスとかとらせて何故ボーカルをやらせないんだと(笑)。
―――ピンクってミュージシャン・エゴのぶつかりあいで良い作品が生まれるっていうイメージがありますが。
岡野:ベースで主張なんかしたりしません、私は。
ホッピー:一個の楽曲に対して、自分の思い入れとか演奏以外の面で、どうしても譲れないものがあるでしょう。そうした場合、他の人間は楽器でしかない訳であって。
岡野:プレイヤーとしてのフィールドは、ピンクではどうしても、ライヴとかあるから、強く出てしまうけれども。自分の楽器以外のフィールドに出ていく場合、どこまでやっていいものか、大変な問題な訳です。「私はこの曲が嫌いです」と言ってしまったら、そこでストップしてしまう。バンド、特にピンクの場合はメンバーが凄いから、敬意も払いますしね。
ホッピー:この二人以外の曲で誰かが我を通した場合、僕達が我を通したら作業としてその曲は潰れてしまうでしょう。だから、一歩引いてね。いかに盛り上げていくかって方向に専念するの。それが今まで多かった訳、仕様がないから。イヤだったんだけどね。
―――では、今回の”作家主義”的なアプローチは、有意義だったんですね。
ホッピー:絶対いいと思う。曲を作った人間が中心になってコンセプトを作っていくのは、作品に対してイロも出てくると思うしね。本来バンドというのは、メッセージを投げかけていく上で、一つになっている方が美しいんだけれども。ただ、こんな方法をとっていたら、エゴは通るけれども、バンドとしてのパワーは薄れてしまうね。
―――では、今後もこの方針で行く訳ではないんですね。
岡野:それは全然わかりません。最初にあったコンセプトがCDのサイズでやろうっていう事があって。内容に入る前にね。今まではアナログ盤という物理的状況を満たすために、イントロやソロを短くしたり、苦しい作業を強いられていた訳だけれども。今回は収録時間も長いから、長い曲・小曲に拘らず、みんなで作品を出しあおうって事であってね。
―――もし、二人が『サイバー』をプロデュースするとしたら、今回の様にしましたか。
岡野:もっとスキャンダラスで、メチャクチャな作品にしたかったな。せっかく特殊な器があるんだから。聴き易さとか考えずに。
ホッピー:曲を持ち寄るって事は、本来バンドのあるべき姿なんだよね。でも、今回の作品は曲数があって幅があるからこそ出来るものでね。もっと密度の濃い、集約したものだと、例えば他の人間がボーカルをとるとか、出来にくいよね。ピンクを相手にした場合、どんな形になるのか想像もつかないな。
―――福岡ユタカさんのボーカルについては、ピンクの表看板とも言える程、個性的ですが。
岡野:確かに優れた素材とは思いますね。独特の声質をもっているし。
ホッピー:声質という点では、独特のものがあるから彼の世界は必ず作れますよね。ただ、それに頼りすぎる時があるね。詩を解釈して、相手に伝達しようという部分が、弱い。
―――ピンクの詩についてはどうですか。いわゆるメッセージ・ソングや単純なラブ・ソングとは一線を画している様ですが。
岡野:あれはメッセージじゃないでしょう。ああいう歌をメッセージとは思わない。ピンクの歌は、全てとは言いませんけど、メッセージ・ソングです。拳を振り上げてとか言うんじゃなくて、もっと深い意味でね。その辺の見解が、僕と福岡君とは相当な隔たりがあると感じますね。何故かはわからないけど。
ホッピー:生半可な只のラブ・ソングではないからね。それをどういう思想背景で歌うかって事が問題であって。ストレートなものがメッセージって訳じゃないから。ストレートじゃないメッセージをどういう風に表現するのか、ピンクの詩では要求されるものが大きいよね。
―――ビジュアル・ワークへの関心は。
岡野:本当は全部やりたい。ジャケットからビデオからステージの構成、衣裳・・・・・。但し、ピンクでそれをやろうとは思わないな。大変すぎるからなぁ(笑)。お金を凄くくれるなら、やってみたいけど。
ホッピー:それはある(笑)。お金の事も踏まえて、総合的なプロデュースとかは、日本のシステムでは難しいね。いつも、レコーディング等で参加する時は、いろいろ言うんだけれども。悔しい思いを、いつもしている。
岡野:今、欲しいのは金と権力です(笑)。才能とアイデアと、ノウハウはもうあるよ。それさえあれば、全部ひっくり返してみせる(笑)。
―――バンド少年・少女達に何か、コメントを。
岡野:音楽家が音楽だけで完結してはダメだよ。音楽しか語れないのは、ナンセンスじゃないか。もっと大きな眼で見る事がビートにつながると思う。生きている事自体がバイブレーションなんだから。先程のメッセージっていうのは、そういう所から出てくると思う。
ホッピー:ロックとかパンクとかっていうのは音楽の形態じゃなくて、生活とか生き方が太いって事だよね。僕達はロック・ミュージックっていう夢を売っている訳だから、派手に”花”でいたいね。理屈じゃないところで、音楽をやっていきたいな。
(インタビュー・文:田井敏晴、撮影:加藤 忠)
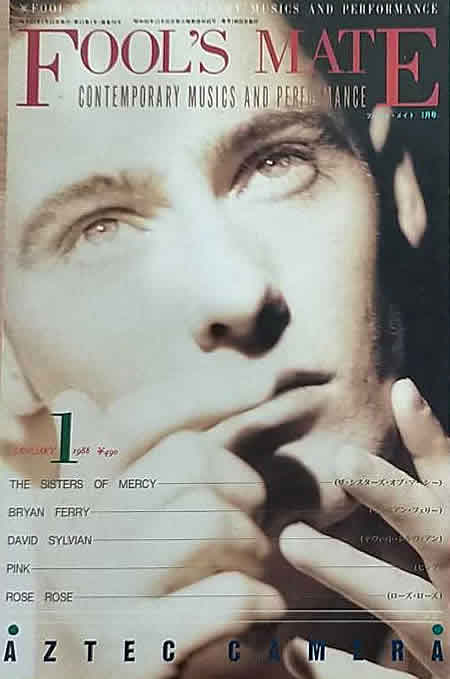 「FOOL’S MATE」1988年1月号掲載
「FOOL’S MATE」1988年1月号掲載



