
エンちゃんこと福岡ユタカは声が大きい。言葉はていねいだが、言うことはかなり向こうっ気が強い。テクニックあるメンバーが揃い、演奏力がウリのユニットというイメージもあるピンクだが、インタビューしてみて、あらためて彼のリーダー・シップを痛感した。ヤワな歌謡ロックは蹴散らす、鋭角な個性を持ったロック・ヴォーカリストの登場。僕はすでにライブ・インに毎月足を運び始めている、彼の歌声の熱心なファンだ。
―――デビュー・アルバムが出るまで随分時間がかかりましたよね。その間はかなりフラストレーションもあったんじゃないですか?
「そりゃたまるでしょう。他のメンバーは人のバックとかやってるしね、お仕事とはいえ。普通あれだけのことがあると解散してると思うんだけれど、僕はともかく歌をやめるつもりはなかったし、他のメンバーもいろいろ仕事をしつつもロックをやりたいって気持ちが強かったから、結局、状況的なこともあってこの6人に固まったって感じですよね。でも、作りたいものが作れたから、今は満足してます。」
―――アルバムの曲はいつ頃書いたものが多いですか?
 「シルバー・サイド(A面)はずっとライヴで演ってた曲で、ゴールド・サイド(B面)の方は新しい。ただ「ソウル・フライト」は2年以上前に「ソニー・ミュージック・TV」のテーマ曲として一度録ってますね。今度のもアレンジはその時とほとんど変わってない。ともかく、手法的なものとかは自分達の中で出来あがっちゃってたんで、むしろどういう部分を削るかを考えて作りました。やりたいことは一杯あるんだけれども、あえてシンプルに。」
「シルバー・サイド(A面)はずっとライヴで演ってた曲で、ゴールド・サイド(B面)の方は新しい。ただ「ソウル・フライト」は2年以上前に「ソニー・ミュージック・TV」のテーマ曲として一度録ってますね。今度のもアレンジはその時とほとんど変わってない。ともかく、手法的なものとかは自分達の中で出来あがっちゃってたんで、むしろどういう部分を削るかを考えて作りました。やりたいことは一杯あるんだけれども、あえてシンプルに。」
―――特にゴールド・サイドはすごく音数を抑制してますね。
「そうです。僕としては、ゴールド・サイドの方に思い入れが強くて、詩の面でもすごく好きですね。派手さはないですけれど。」
―――僕もこっちの方が新鮮でした。
「そう言われると、嬉しい。ただ、両面の温度差がありすぎて、困りました。こっちの曲は透き通った感じで熱くならないから。どう並べようか色々考えて、結局こうなったんです。」
―――曲作りにしても、覚えやすいフックを使って、というような感じじゃないでしょう。何度か聞かないと分からない微妙な揺れがあって・・・。
「いわゆる歌謡ロックみたいのはやりたくないから。シングルを切る予定もなかったし、そういうのはみんなお仕事でやってるしね。新しい音使うとかもCFの仕事でいくらでもできるでしょう。だから、逆に自分達のLPじゃサンプリング音とか派手に使うのは嫌になった。過剰アレンジをやめようということで・・・。」
―――イギリスでも、例えばティアーズ・フォー・フィアーズの新作なんかはオーソドックスな肉体感のある演奏を打ち出してきていますよね。
「うん、また詩と曲の時代に戻ってきた気がする。だから、ポピュラーなものを作る人とニューウェイブの新しいものを作る人の位相がズレてきて、おのおのの位置に帰っていったっていうか、ひとつ祭りが終わったみたいなところがあるのかもしれない。アートはアートに帰っていって、ファッションはファッションに、ロックはロックにっていう。僕は欲張りだからそれを混ぜ合わすのが面白いと思うんですけれど。」
―――6人の中では、誰が発言力が強いとかあるんですか?
「基本的には僕の我が儘を全部通すんですけれど、やっぱり岡野(ハジメ)くんとカメちゃん(矢壁アツノブ)でしょうね。リズムに関してはこのふたりに任せちゃうところも多いし。あとの楽器はウラメロとかコードの一番上の音とかを僕が指定して、音色的なことはみんなウルサイですね。ミキサーの卓とかも自分でいじるし。そういう意味じゃ大変なバンドですよ。アレンジも自分達だし、ホントすべてセルフ・プロデュース。コスチュームとかもみんなアーダコーダ言うし、自分だけのスタイリスト連れてくる人もいる(笑)。でも、そうじゃないと面白くならないでしょう。人に任せたくないんです。」
―――ロックも今はかなりプロデューサーの音楽になってるから・・・。
「そうですね。特にソロの人は誰が曲書いて、誰がアレンジしてっていうコーディネーションで音楽が出来ていくのが多い。アメリカなんかでもそうだし、そういう意味じゃすごく日本の歌謡曲的になっている。ロックっていうものが構造に吸い取られちゃってね、もうドロップ・アウトの音楽でもないでしょう。みんなコレ(上昇指向)だものね。一番ロックっぽいプリンスだってそれがチラつくし、だから、ロックっていう方法論はもう終わっちゃってるところもあるんだけれど、ただアーティスティックな意味ではまだまだやれることはあるから。」
―――ライブでもっとインプロヴィゼーションを拡大したりというアイデアはないんですか?
「う~ん、みんなそういう指向は無いんですよね。むしろ僕の方が望んでいるぐらいで・・・。たぶん、そういうのも徐々にやっていくと思いますけれど。あと、極端なグラム・ロックの曲を作るとか、デビューLPってことでやらなかった部分も、どんどん出していこうと思っています。」
(インタビュー・構成/高橋健太郎)

「シティ・ロード」1985年6月号掲載
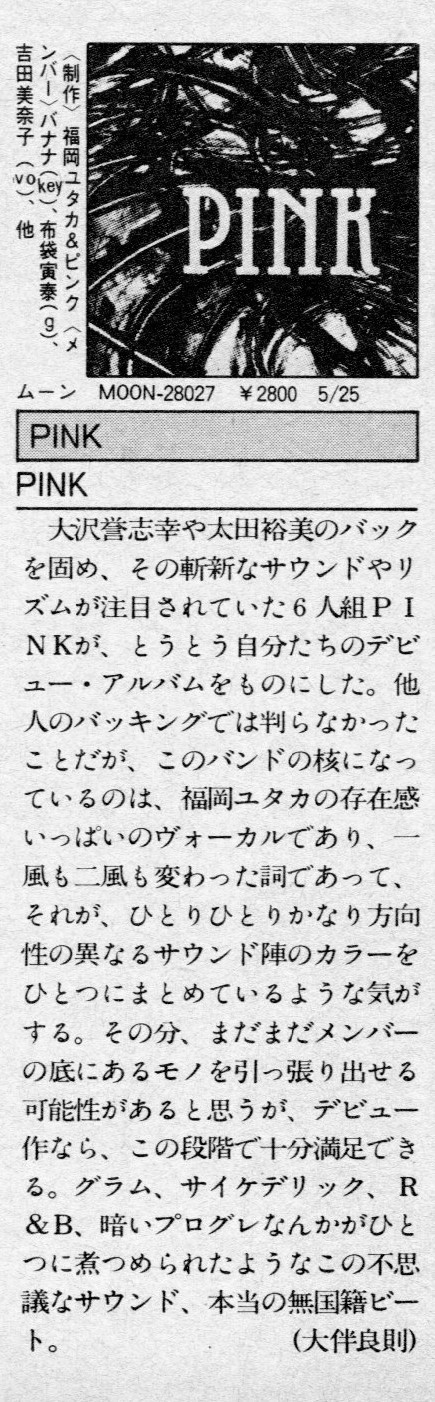
【アルバムレビュー】
大沢誉志幸や太田裕美のバックを固め、その斬新なサウンドやリズムが注目されていた6人組PINKが、とうとう自分たちのデビュー・アルバムをものにした。
他人のバッキングでは判らなかったことだが、このバンドの核になっているのは、福岡ユタカの存在感いっぱいのヴォーカルであり、一風も二風も変わった詞であって、それが、ひとりひとりかなり方向性の異なるサウンド陣のカラーをひとつにまとめているような気がする。
その分、まだまだメンバーの底にあるモノを引っ張り出せる可能性があると思うが、デビュー作なら、この段階で十分満足できる。
グラム、サイケデリック、R&B、暗いプログレなんかがひとつに煮つめられたようなこの不思議なサウンド、本当の無国籍ビート。
(大伴良則)
 「シティ・ロード」1985年6月号掲載
「シティ・ロード」1985年6月号掲載


