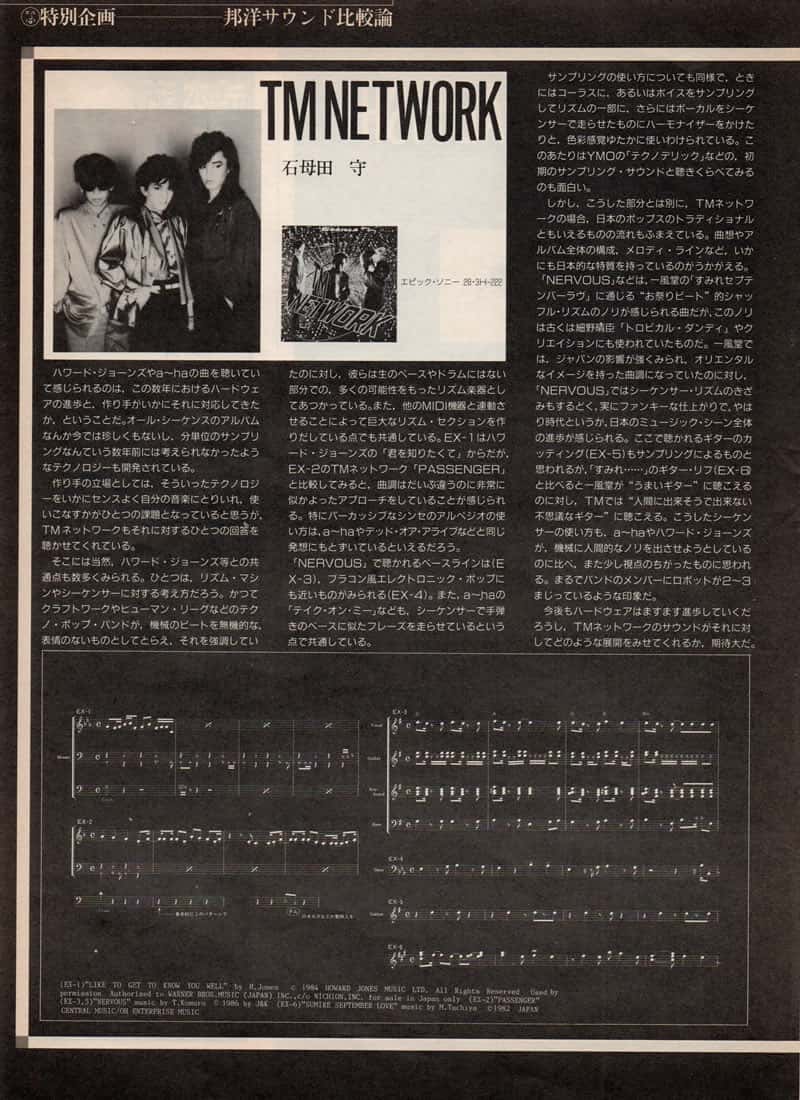(1) 日本のロックの祖はダークダックス
(2) 海外進出も盛んになった’80年代の和製ロック
(3) 佐野元春 with THE HEARTLAND
(4) PINK
(5) KUWATA BAND
(6) REAL FISH(リアル・フィッシュ)
(7) TM NETWORK
(8) REBECCA(レベッカ)
ハワード・ジョーンズやa~haの曲を聴いていて感じられるのは、この数年におけるハードウェアの進歩と、作り手がいかにそれに対応してきたか、ということだ。オール・シーケンスのアルバムなんか今では珍しくもないし、分単位のサンプリングなんていう数年前には考えられなかったようなテクノロジーも開発されている。
作り手の立場としては、そういったテクノロジーをいかにセンスよく自分の音楽にとりいれ、使いこなすかがひとつの課題となっていると思うが、TMネットワークもそれに対するひとつの回答を聴かせてくれている。
そこには当然、ハワード・ジョーンズ等との共通点も数多くみられる。ひとつは、リズム・マシンやシーケンサーに対する考え方だろう。かつてクラフトワークやヒューマン・リーグなどのテクノ・ポップ・バンドが、機械のビートを無機的な、表情のないものとしてとらえ、それを強調していたのに対し、彼らは生のベースやドラムにはない部分での、多くの可能性をもったリズム楽器としてあつかっている。また、他のMIDI機器と連動させることによって巨大なリズム・セクションを作りだしている点でも共通している。EX-1はハワード・ジョーンズの「君を知りたくて/Like To Get To Know You Well」からだが、EX-2のTMネットワーク「PASSENGER」と比較してみると、曲調はだいぶ違うのに非常に似かよったアプローチをしていることが感じられる。特にパーカッシブなシンセのアルペジオの使い方は、a~haやデッド・オア・アライブなどと同じ発想にもとづいているといえるだろう。
「NERVOUS」で聴かれるベースラインは(EX-3)、ブラコン風エレクトロニック・ポップにも近いものがみられる(EX-4)。また、a~haの「テイク・オン・ミー」なども、シーケンサーで手弾きのベースに似たフレーズを走らせているという点で共通している。
サンプリングの使い方についても同様で、とににはコーラスに、あるいはボイスをサンプリングしてリズムの一部に、さらにはボーカルをシーケンサーで走らせたものにハーモナイザーをかけたりと、色彩感覚ゆたかに使いわけられている。このあたりはYMOの「テクノデリック」などの、初期のサンプリング・サウンドと聴きくらべてみるのも面白い。
しかし、こうした部分とは別に、TMネットワークの場合、日本のポップスのトラディショナルともいえるものの流れもふまえている。曲想やアルバム全体の構成、メロディ・ラインなど、いかにも日本的な特質を持っているのがうかがえる。
「NERVOUS」などは、一風堂の「すみれセプテンバーラヴ」に通じる”お祭りビート”的シャッフル・リズムのノリが感じられる曲だが、このノリは古くは細野晴臣「トロピカル・ダンディ」やクリエイションにも使われていたものだ。一風堂では、ジャパンの影響が強くみられ、オリエンタルなイメージを持った曲調になっていたのに対し、「NERVOUS」ではシーケンサー・リズムのきざみもするどく、実にファンキーな仕上がりで、やはり時代というか、日本のミュージック・シーン全体の進歩が感じられる。ここで聴かれるギターのカッティング(EX-5)もサンプリングによるものと思われるが、「すみれ・・・・」のギター・リフ(EX-6)と比べると一風堂が”うまいギター”に聴こえるのに対し、TMでは”人間に出来そうで出来ない不思議なギター”に聴こえる。こうしたシーケンサーの使い方も、a~haやハワード・ジョーンズが、機械に人間的なノリを出させようとしているのに比べ、また少し視点のちがったものに思われる。まるでバンドのメンバーにロボットが2~3まじっているような印象だ。
今後もハードウェアはますます進歩していくだろうし、TMネットワークのサウンドがそれに対してどのような展開をみせてくれるか、期待大だ。
(石母田 守)
PASSENGER(TM NETWORK)
Like To Get To Know You Well(Howard Jones)
NERVOUS(TM NETWORK)
すみれ September Love(一風堂)
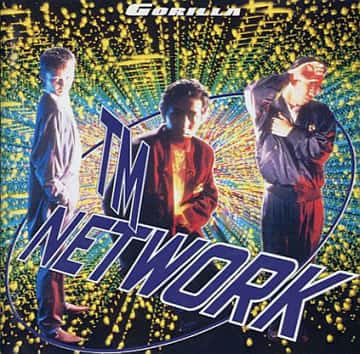
アルバム『GORILLA』1986年6月リリース